【酒税法 合格体験記】効率学習で突破!勉強時間と戦略を公開|令和6年度 税理士試験
酒税法を選択した理由
法人税法のような大型税法と比べ、酒税法は出題範囲がコンパクトで、比較的短期間で合格を狙える科目とされています。
私は簿記論・財務諸表論に合格した翌年(令和5年度)、「負担を最小限にするため」に酒税法を選択しました。結果的に合格したのは令和6年度です。
同時に国税徴収法も受験しましたが相性が悪いと感じ、のちに固定資産税へ切り替えています。
酒税法は計算問題の比重が高く、出題パターンがある程度決まっているため、効率的な学習が合格のカギだと痛感しました。理論の暗記量は税法の中で最も少ない部類だと思います。
勉強時間とスケジュール
総学習時間
酒税法にかけた勉強時間はおよそ 900時間。
法人税法よりは少なかったものの、結局は 2年かかり想定以上に大変 でした。
平日・休日の学習ペース
- 平日:1~2時間(判定問題+理論の音読)
- 休日:4~5時間(判定問題+理論音読または手書き)
- 直前期:過去問・答練を徹底的に回す
学習の流れ
- 1月~4月:講義・基礎固め、判定問題、理論音読・手書き
- 5月~本番:頻出理論の反復暗記+計算問題演習
勉強スタイルと使用教材
酒税法はマイナー科目のため、市販教材は少なく、私は 予備校のテキスト・問題集 を中心に学習しました。
学習の工夫
- 頻出理論を優先して暗記
- 計算はシンプルな分、ケアレスミスを徹底排除
- 「狭い範囲=落としたら致命的」なので正確性を最重視
実際、1回目の受験では 基本問題のビール判定を誤って不合格 になりました。
理論問題は「誰も書けない問題」は割り切って捨て、得点源を確実に取る方針で臨みました。
試験当日の印象と戦略
法人税法に比べ、会場の雰囲気は落ち着いていました。出題は「理論+計算」の基本パターンです。
当日の戦略
- 計算から着手(90分程度を計算に集中)
- 理論は「書けるところから書く」
- 難問は深追いせず、確実な得点を優先
結果、大きな崩れなく乗り切ることができました。
合格したときの気持ちと学び
合格を知ったときは、「大きな山(法人税法)の後に、予定通り一歩進めた」という安堵感が大きかったです。
学んだことは:
- 小さい科目でも油断は禁物
- 理論暗記は「範囲が狭い分、正確さとスピードが勝負」
- 合格を積み重ねることでモチベーションが維持できる
酒税法を振り返って
酒税法は「短期集中で合格しやすい」と言われますが、出題範囲が狭いため 1つの失点が命取り になります。
法人税法と並行して学んだからこそ、酒税法では「効率的な学習」と「確実な得点力」の重要性を痛感しました。
まとめ|酒税法合格のポイント
酒税法合格に必要だと感じたことは以下の通りです。
- 600~700時間の学習を目安に確保(得意な人はもっと短縮可能)
- 頻出理論を優先的に暗記し、何度も繰り返す
- 計算はケアレスミス防止を徹底
- 本番は「計算で満点狙い、理論は暗記したものは必ず書く」で安定感を出す
酒税法は法人税法など大型科目と組み合わせやすく、全体のバランスを取りやすい科目。
地道に取り組めば、確実に合格につながると思います。
※「満点」と書いていますが、実際は満点でなくても合格できます。ただ、普段から満点を狙っていないと本番で高得点を取ることはできないと思っているので、この表現を使っています。100点狙って準備しないと80点は取れません。本番は独特の緊張感と、失敗したらまた来年というプレッシャーの中で受験します。手は震えますし、口は乾きますし、そのような極限状態で穏やかな状態の自分を維持できる人が世の中どのくらいいるでしょうか。私は、税理士試験を通して自分がいかに無能で凡庸であるかを理解できました。無能なら無能なりの考え方、戦い方があるとわかりこのブログに書いてあるような、地味な方法で勉強し続けてきました。

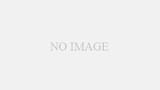
コメント